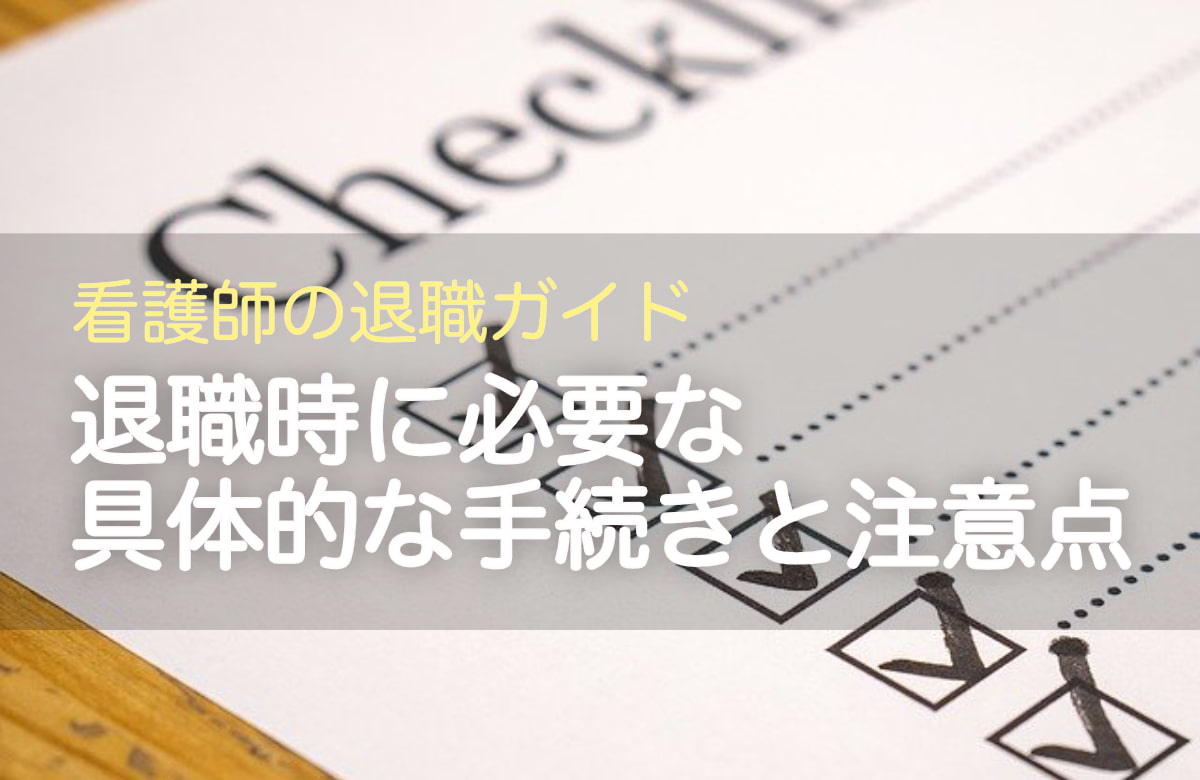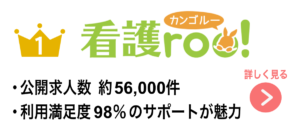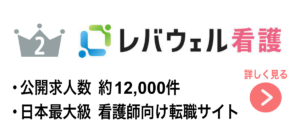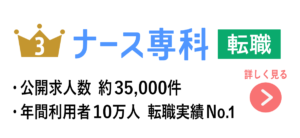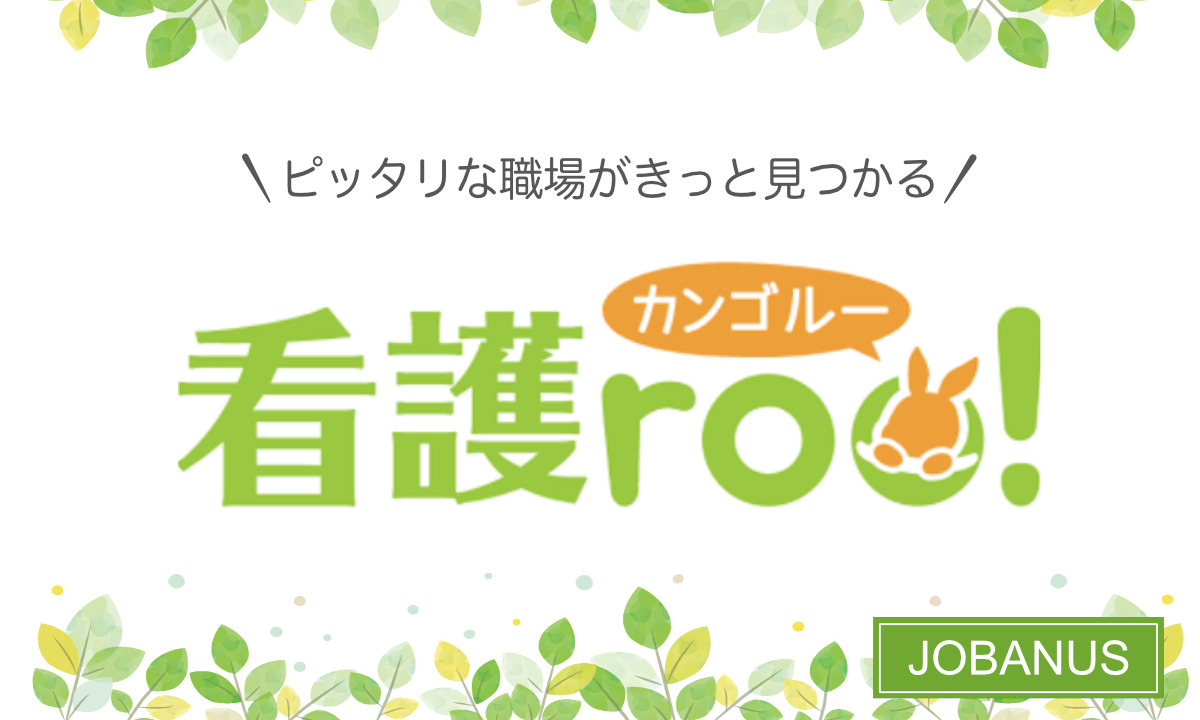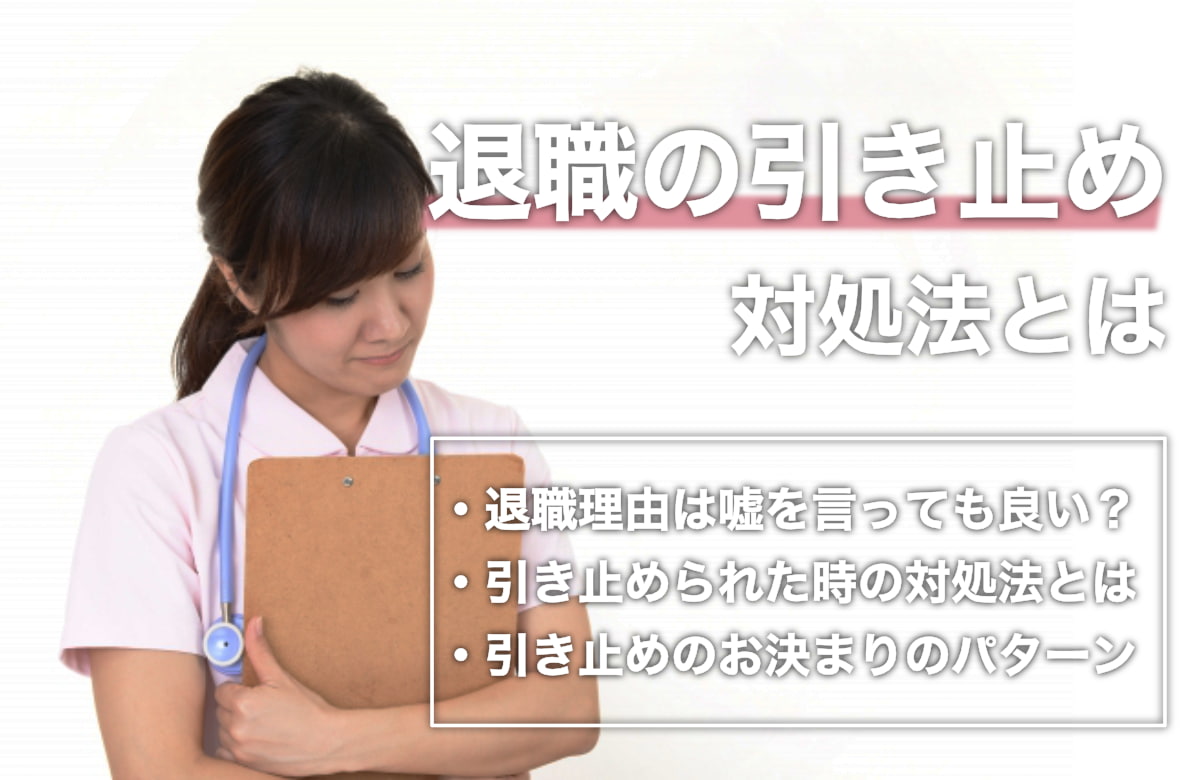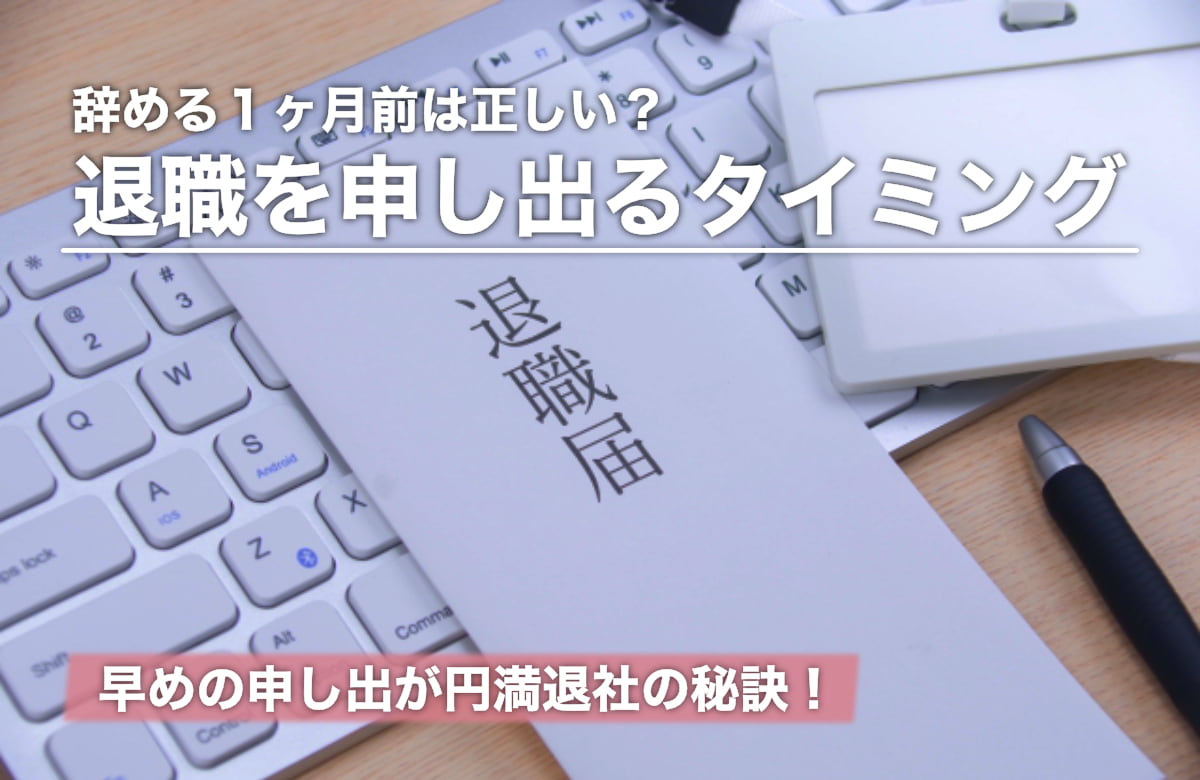- 「結婚後の保険の切り替え、どうすればいいの?」
- 「退職の手続き、何から始めたらいいんだろう…」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
看護師として働きながら結婚に伴う退職手続きを進めるのは、想像以上に複雑で時間がかかるものです。
本記事では、以下のポイントについて詳しく解説していきます。
- 退職時に必要な手続きと提出書類の全体像
- 健康保険・年金・失業保険の具体的な切り替え方法
- 住民税や所得税の取り扱いについての注意点
この記事を最後まで読めば、結婚に伴う退職手続きの流れが把握でき、慌てることなく計画的に準備を進められるようになります。ぜひ最後までご覧ください。
1. 退職時に返却するもの
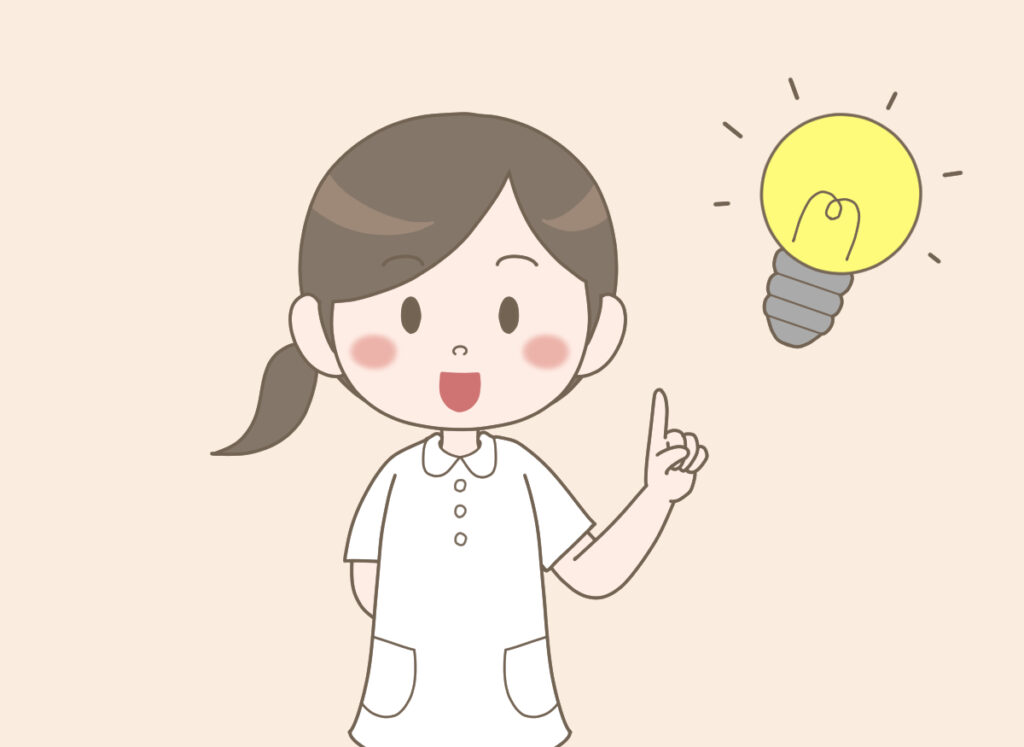
退職時には、勤務中に会社から貸与された物品や支給された備品を適切に返却する必要があります。返却漏れがあると、後々のトラブルの原因となる可能性があるため、慎重な確認が重要です。
この章では、退職時に返却が必要な主な物品について詳しく解説していきます。
1-1. 健康保険証
医療機関を受診するときに必要な健康保険証ですが、退職すると社会保険の被保険者ではなくなるため、返却が必要です。
前職で交付された健康保険証は退職後に使うことができませんので、健康保険証を新たに発行してもらう必要があります。
すぐに新しい職場が決まれば健康保険証を発行してもらえますが、離職期間がある場合は次の3つのいずれかの手続きを行う必要があります。
- 自治体の国民健康保険に加入
- 現在交付されている健康保険証の任意継続
- 家族の健康保険の扶養になる
前職の退職日から現職の入職日までの期間のこと。例えば、前の会社を12月31日に退職し、2週間ほど転職活動をした後に現在の病院に4月1日に入職した場合は、離職期間は3ヶ月になります。
いずれの方法も、すぐに新しい健康保険証が発行されませんので、手続きの期間は無保険になります。

前職で交付された健康保険証は、①~③のどの手続きを選択したとしても、必ず返還する必要があります。医療費は通常3割負担ですが、無保険の期間は一旦10割(全額)を負担する必要がありますので、病気や怪我には十分ご注意ください。
1-2. 通勤定期券
職場への通勤手段にもよりますが、公共交通機関を使っていた場合は通勤定期券を返却する必要があります。
電車やバスを使って通勤していた方の中には、「引き続き使えたらラッキー!」と思う方もいるかもしれません。
ただ、残期間が長い場合は返却や払い戻しをして返金しなければならないケースがほとんどです。会社ごとに規定が異なるので、分からない場合は上司に確認してください。

1年定期で11ヶ月が過ぎている場合は、返却不要と言われるかもしれません。一方、6ヶ月定期で1ヶ月しか経過していない場合は、確実に返却を求められるでしょう。
1-3. 職場で支給された備品
職場から貸与されているパソコン、セキュリティキー、鍵など「備品」と呼ばれるものは、返却しなければなりません。
返却しないと後々トラブルになることもありますので、注意が必要です。「病院から預かっているものは全て返却する」というくらいの意識でいると間違いないでしょう。
もし返却が必要か迷った場合は、上司に確認すると良いでしょう。
2. 退職時に受け取るもの
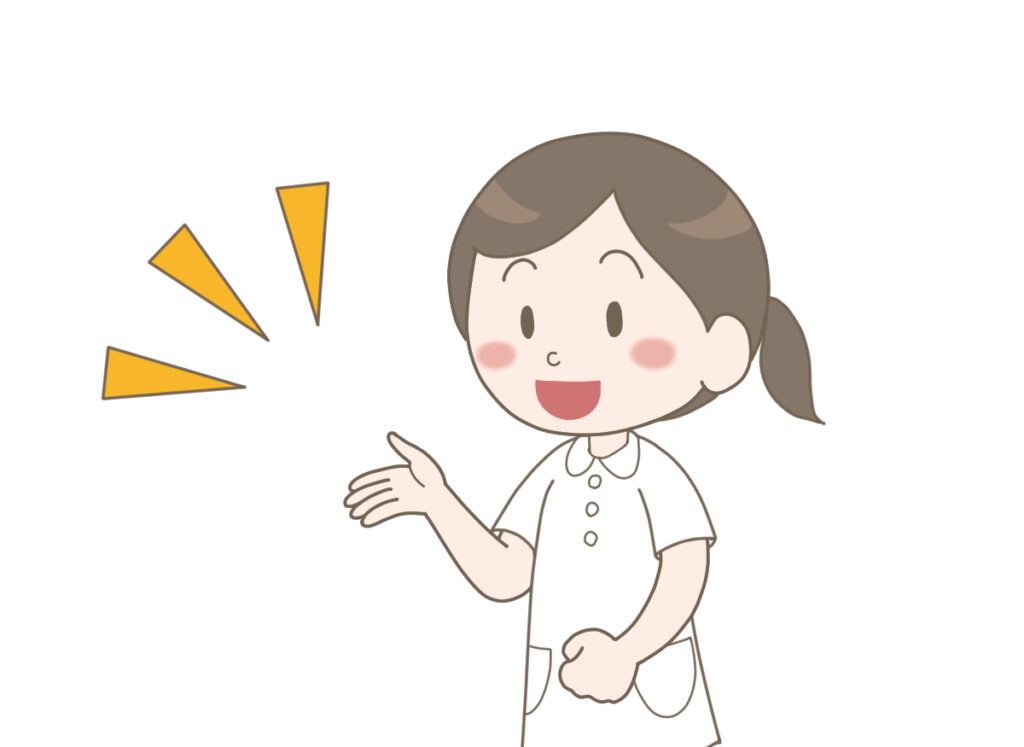
退職時には、会社から受け取るべき重要な書類があります。雇用保険被保険者証や源泉徴収票、年金手帳など、退職後の生活や手続きに必要不可欠なものが含まれています。
この章では、退職時に受け取るべき書類について、詳しく解説します。
2-1. 雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、失業給付を受けるために必要な重要書類です。退職時には必ず受け取るようにしましょう。
この証明書には、以下の重要な情報が記載されています。
- 雇用保険被保険者番号
- 勤務先の事業所名
- 被保険者となった年月日
- 離職年月日
入職時に既に返却されている場合もありますが、紛失してしまった場合はハローワークで再発行が可能です。再発行には雇用保険被保険者番号が必要となりますので、会社の人事部門に確認してください。
この書類は失業給付の手続きで使用する離職票の発行にも必要となります。大切に保管しておきましょう。
2-2. 源泉徴収票
源泉徴収票は退職時に必ず受け取るべき重要書類です。この書類には、あなたの給与総額と納付済みの所得税額が記載されています。
源泉徴収票は通常1月から12月までの期間で発行されますが、年の途中で退職する場合は、退職時までの期間で発行されます。この書類は転職後の手続きに必要不可欠で、特に以下の場面で使用します。
- 転職先での年末調整手続き
- 確定申告の際の所得証明
- 雇用保険の受給手続き
転職先が決まっている場合は、年末調整のために新しい職場へ提出することになります。一方、年内に転職先が決まらない場合は、確定申告が必要となりますが、この手続きによって場合によっては所得税が還付される可能性もあります。
また、退職時の源泉徴収票は、将来の年金受給額の計算にも影響する大切な書類です。紛失した場合は再発行を依頼できますが、手続きに時間がかかる場合があります。
2-3. 年金手帳
年金手帳は退職時に必ず確認・受け取りが必要な重要書類です。将来の年金受給に関わる大切な記録が含まれています。
年金手帳には、あなたの基礎年金番号が記載されており、この番号は生涯使用する固有の番号となります。転職時には新しい勤務先への提出が必要となるため、以下の点に特に注意が必要です。
- 会社が保管している場合は必ず返却を依頼する
- 手元にない場合は保管場所を人事部に確認する
- 紛失している場合は退職前に再発行手続きを行う
年金手帳は健康保険の切り替えや雇用保険の手続きにも必要となります。また、転職後の厚生年金の手続きにも使用するため、スムーズな手続きのためにも必ず手元に用意しておきましょう。
なお、紛失した場合は最寄りの年金事務所で再発行が可能です。ただし、再発行には本人確認書類が必要となり、手続きに時間がかかる場合があります。
2-4. 離職票
離職票は失業手当を受給するために必要不可欠な書類です。退職後の生活を経済的に支える重要な保障となります。
離職票には以下の重要な情報が記載されています。
- 雇用保険被保険者番号
- 勤務期間と退職日
- 退職前の賃金
- 退職理由
退職が決まったら、会社に離職票の発行を依頼してください。通常、退職日から10日以内に会社から自宅に郵送されます。離職票は失業手当の申請に必須のため、届かない場合は以下の対応が必要です。
- まずは前職の人事担当者に確認の連絡
- 連絡しても解決しない場合はハローワークに相談
失業手当の受給を円滑に進めるため、離職票が届いたらすぐにハローワークで手続きを行いましょう。手続きが遅れると、その分だけ受給できる期間が短くなる可能性があります。
3. 年金・健康保険・失業手当の手続きについて

退職後の生活を安定させるためには、年金や健康保険、失業手当の手続きを適切に行う必要があります。手続きの方法は、離職期間の有無や雇用保険加入期間によって異なるため、自分の状況に合わせた手続きを行うことが重要です。
この章では、年金・健康保険・失業手当の手続きについて、状況別に詳しく解説します。
3-1. 離職期間がある+雇用保険加入期間12ヶ月未満
雇用保険の加入期間が12ヶ月未満の場合は、「年金」と「健康保険」を新たなものに切り替える必要があります。
失業手当は、雇用保険加入期間(在職期間)が短いため受け取る権利はありません。
3-2. 離職期間がある+雇用保険加入期間12ヶ月以上
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上の場合も、「年金」と「健康保険」の切り替えが必要ですが、このケースでは「失業手当」を受給できる可能性があります。
離職票を受け取ったら早急に手続きを進めましょう。
「年金」の手続きはこちら
「健康保険」の手続きはこちら
「失業手当」の手続きはこちら
3-3. 離職期間がない(退職日の翌日に入職)
既に転職先が決まっており離職期間がない場合は、転職先があなたに代わって年金と健康保険の手続きを行ってくれますので、必要な書類を転職先に提出しましょう。
転職先に提出する必要がある書類は、次のとおりです。
4. 年金の切り替えについて

公的年金には大きく分けて第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。
第2号被保険者、第3号被保険者でない人。0歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が該当。
厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者である人。民間会社員や公務員の人が該当。
国民年金の加入者のうち、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人が該当。保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、国民年金の第1号または第3号のいずれかの被保険者となります。
そのため、退職した場合は「第1号被保険者」または「第3号被保険者」への切り替えが必要となります。
それでは、1号被保険者と3号被保険者の違いや特徴を見てみましょう。
4-1. 第1号被保険者とは
| 区分 | 要件 |
| 手続きの期間 | 退職後14日以内 |
| 手続きの場所 | 市区町村の年金窓口 |
| 必要なもの | 年金手帳、印鑑、離職票など退職日のわかるもの |
病院を退職した方で、第3号被保険者(配偶者の扶養)に該当しない20歳以上60歳未満の方は、第1号被保険者に加入する必要があります。
手続きは、お住いの市区町村の年金窓口で、14日以内に行ってください。
1号被保険者は納める保険料は少ないため、厚生年金と比べて受け取れる年金額も少ないのが特徴です。具体的には、満額で780,900円(2021年度時点)、月額に換算すると65,075円となります。
未納、免除、カラ期間があると、ここからさらに減額されます。

収入が少ないなど、保険料を納めることが困難な方向けに免除・猶予制度あります。
詳しくは国民年金機構HPをご参照ください。
4-2. 第3号被保険者とは
| 区分 | 要件 |
| 手続きの期間 | 退職後14日以内 |
| 手続きの場所 | 配偶者の勤務先 |
| 必要なもの | 年金手帳、印鑑、離職票など退職日のわかるもの |
厚生年金を収めている2号被保険者(会社員・公務員の配偶者)に扶養される20歳以上60歳未満の方は、その扶養に入ることが可能です。
第3号被保険者に関する手続きは、配偶者の勤務先で行う必要があります。役所では手続きできませんので、ご注意ください。
第1号被保険者と同様に受け取れる年金は基礎年金部分のみになりますので、第2号被保険者(厚生年金)と比べて受給額は少なくなります。
なお、健康保険と違い、配偶者以外の家族の扶養に入ることができません。そのため、配偶者がいない場合は必然的に1号被保険者となります。
5. 健康保険の切り替えについて

結婚に伴う退職では、健康保険の切り替えは避けては通れない重要な手続きの一つです。加入する保険の種類によって手続きの方法や期限が異なるため、慎重な検討が必要になります。
この章では、健康保険の切り替えに関する選択肢とそれぞれのメリットについて解説していきます。
5-1. 現在の健康保険を任意継続する
| 区分 | 内容 |
| 手続きの期間 |
|
| 保険料 |
|
| おすすめする方 |
|
| 主な特徴 |
|
退職前に健康保険の被保険者である期間が2ヶ月以上あった場合は、最大2年間まで任意継続することが可能です。
任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内に行う必要があります。これを過ぎると任意継続を利用できなくなりますので、ご注意ください。
任意継続しても、これまでと同じ保険給付及び保健事業を受けることができます。
任意継続を選択しない場合は国民健康保険に加入することになりますが、退職1年目は前年所得(現役時代の所得)で保険料を計算するため、任意継続の保険料よりも高くなる場合があります。
そのため、任意継続と国保のどちらの保険料が安いのか、試算してもらいましょう。
5-2. 市区町村の国民健康保険に加入する
| 区分 | 内容 |
| 手続きの期間 |
|
| 手続きに必要なもの |
|
| 保険料 |
|
| おすすめする方 |
|
| 主な特徴 |
|
国民健康保険は、市区町村が運営する健康保険です。加入する場合は、住民票のある市区町村の国保窓口で、退職日の翌日から14日以内に手続きしてください。
世帯全員の保険料が世帯主に一括請求られるのも国保税(料)の特徴です。仮に世帯主が国保に加入していなくても、納入義務者は世帯主になる(擬制世帯主)ことに注意が必要です。

擬制世帯主は国保税(料)の納税義務者になりますが、保険税(料)の計算の中には入りませんのでご安心ください。
5-3. 家族の扶養に入る
| 区分 | 内容 |
| 手続きの期間 |
|
| 保険料 |
|
| おすすめする方 |
|
| 加入の要件 |
|
退職後すぐに転職をしないのであれば、家族(親や配偶者)の扶養に入ることもできます。扶養に入る場合は、ご家族が加入する健康保険組合で手続きが必要ですので、速やかに申し出ましょう。
扶養に入る場合は、年収が130万円未満で、かつ同居の場合は被保険者の年収の1/2未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満である必要があります。
6. 失業手当を受け取る条件と手順について

退職後の生活を支えるために、失業手当の受給は重要な選択肢の一つです。しかし、失業手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があり、手続きも複雑です。
この章では、失業手当を受け取る条件と手順について、詳しく解説します。
6-1. 失業保険を受け取るための条件
失業手当を受け取るためには、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
- いつでも就職できる能力があるが、就職業できない
- 退職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上ある
そのため、次の方は①の条件により失業手当を受け取ることができません。
- 退職してすぐに就職する意思がない人
- 病気やケガ、妊娠・出産などですぐに就職するのができない人
6-2. 失業手当の受給までの流れ
失業手当は申請してすぐに受け取れるわけではありません。
ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があり、特別な事情のある方で1ヶ月、通常は2ヶ月程度かかります。
それでは、失業手当の申請から受け取るまでの流れを見ていきましょう。
- STEP1退職
離職票を受け取る
- STEP2ハローワークで手続きする
求職票に記入し、離職票とともに提出して面接を受ける
- STEP37日間待つ(待機期間)
自己都合や懲戒解雇による退職の場合は、待機期間満了の翌日から2ヶ月間は給付制限のため給付がありません。
- STEP4雇用保険受給者説明会に参加する
受給資格者のしおりに基づき、雇用保険の受給中の諸手続きや失業認定申告書の書き方、不正受給についての留意事項などの説明を受けます。
- STEP5失業認定を受ける(1回目)
認定日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告するなどの手続きを行うことで、職業に就くことができないことの認定を受けます。
- STEP6認定後1週間で給付
- STEP7以降、毎月(4週間に1回)の失業認定と給付の繰り返し
再就職または給付期限修了まで認定と給付を繰り返します。
注意したい点は、退職理由によって失業手当の受給開始時期が異なることです。
具体的には次のような違いがあります。
- 会社都合による退職
→7日間の待機期間後に給付対象 - 自己都合による退職
→7日間の待機期間 + 2ヶ月の給付制限期間後から給付対象
ただし、自己都合であっても正当な理由が認められる場合はこの限りではありません。

詳しくは、お近くのハローワークへお問い合わせください。
6-3. 早めに再就職が決まると「再就職手当」がもらえる
再就職手当とは、雇用保険の受給資格を満たしている人が思いのほか早く再就職先が決まった場合にもらえる手当のことです。
ハローワークが離職者に早く安定した職業について就いてもらうために設けた制度で、別名「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれています。
支給を受けるためには、次の9つの条件を全て満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職前の事業所、また離職前の事業所と密接な関わり合いがない事業所に再就職したものでないこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
再就職手当の額は、次の計算式で計算されます。
所定給付日数の支給残日数 × 50%(又は70%)×基本手当日額 = 再就職手当
| 30歳未満 | 6,760円 |
| 30歳以上45歳未満 | 7,510円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,265円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,096円 |
注)令和3年8月1日現在の額
50%なのか70%なのかは、支給残日数によって決まります。そのため、早く就職したほうがより給付が大きくなる仕組みになっています。
基本手当日額には上限があり、60歳以上65歳未満は7,096円(2021年8月1日現在)です。
7. 住民税や所得税などの税金について

退職後も住民税の支払い義務は継続するため、適切な納付方法を選択する必要があります。状況に応じて選べる納付方法が用意されているので、自分に合った方法を検討することが大切です。
この章では、住民税の支払い方法について具体的に解説していきます。
INDEX
7-1. 住民税の支払い
住民税は、前年(1~12月)の所得に応じて計算され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払う税金(市民税・県民税)です。
在職中は月々の給与から天引き(特別徴収)されますが、退職すると翌年の5月までの残金を次の3つのいずれかの方法で支払う必要があります。
- 役所から送られてくる納付書で分割納付する
- 退職する職場の最終給与から残金を一括天引きする
- 転職先の職場から給与天引きする
どの方法で納めるかは退職時期によって異なりますので、ケース別に見ていきましょう。
①役所から送られてくる納付書で分割納付する
退職日が6/1~12/31の場合は、納付書による納付(普通徴収)に切り替わり、自分で納付する必要があります。
普通徴収の各々の納期限は市区町村によって異なりますが、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めるのが一般的です。
②退職する職場の最終給与から残金を一括天引きする
退職日が1/1~5/31の場合は、5月までの残りの住民税を退職時の給料から一括天引きされます。ただし、一括天引きする住民税が給料より高い場合は、納付書による納付(普通徴収)に切り替わります。
市区町村から納付書が届きますので、期日までに自分で納付することになります。
③転職先の職場から給与天引きする
「給与所得者異動届出書」を職場経由で市区町村に提出すれば、転職先の給与から天引する「特別徴収」を継続することができます。
ただし、退職してから転職まで期間がある場合や、職場で手続きのお願いができない場合は、①または②による納付になります。
7-2. 所得税の支払い
所得税は、その年(1~12月)の所得に応じて計算され、その年に支払う税金(国税)のことです。
所得税の源泉徴収とは、納税者本人に代わって給与や報酬の支払者が所得税を給与から徴収することをいいます。
退職後に失業期間が発生し前年に比べて所得が減少すると、所得税が余分に源泉徴収された状態になりますので、手続きすることで余剰分を返してもらうことができます。
この手続きは、次の2つのケースで方法が異なります。
- 年内に転職した場合
- 年内に転職しなかった場合、年内に転職したが年末調整に間に合わなかった場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①年内に転職した場合
転職先の12月の年末調整で所得税の過不足を精算できますので、自分で手続きをする必要はありません。
給与担当部署に前職分の源泉徴収票や控除証明書(生命保険、地震保険、個人年金などの支払証明書)を提出してください。
②年内に転職しなかった場合、年内に転職したが年末調整に間に合わなかった場合
こちらのケースでは、自分で精算手続きする必要があります。翌年2月初旬から3月15日までに、お近くの税務署か居住地の市区町村で確定申告を行ってください。
確定申告に必要のものは次のとおりです。
確定申告に必要なものは、申告内容によって異なります。

確定申告書を自分で作成できない方は、申告期間中に税務署や市区町村で行われている申告相談をご利用ください。
8. 退職手続きのサポートに強い転職サイト3選

円満退職のためには適切な退職手続きが不可欠ですが、慣れない手続きに戸惑う看護師も少なくありません。そんな時、看護師転職サイトが退職手続きをサポートしてくれます。
中でも「看護roo!」は、求人数の豊富さだけでなく、退職手続きのサポートにも定評があります。専任のキャリアアドバイザーが、手続きに関する疑問や不安に丁寧に対応してくれるため、もれなく手続きを進められます。
ただ、どのサイトも担当者の良し悪しでサポートの質が変わることがあります。そのため、複数のサイトに登録して比較することが重要です。
各サービスでは求人情報の提供だけでなく、履歴書の添削や面接対策も行っています。転職活動を効率よく進めたい方は、2~3社まとめて登録することをおすすめします。
看護師転職サイトは、以下のような理由から、2~3社の転職サイトに登録しておくことで、より自分に合った転職が可能です。
- 様々な求人情報にアクセスでき、選択肢が格段に広がる。
- 自分にぴったりのコンサルタントと出会う確率が上がる。
- 他社の「非公開求人」や「独占案件」にも目を通せる。
- 転職サイトの「弱み」を他社で補うことができる。
もし「このサイトは使えないかも」と思った場合も、メール一つで簡単に退会できます。ですから、転職サイトは2~3社まとめて登録し、多角的に転職活動を進めてみてください。
この章では、JOBANUSがおすすめする看護師転職サイトを3社ご紹介します。
\おすすめ看護師転職サイト3社/
年間利用者は2万人以上!利用者満足度は驚異の96.2%を誇る転職サイト

- 年間利用者2万人で利用満足度96%以上
- 40,000件以上の豊富な求人
- 履歴書と面接サポートが特に手厚い
看護roo!(看護ルー)は、看護師の転職に特化したサイトで、年間2万人以上が利用し、その満足度はなんと96%以上。業界内で高い信頼を集めています。
求人数も40,000件以上と圧倒的で、月給42万円以上や年休150日以上など、好条件の案件も豊富です。特に嬉しいのはLINEでのサポート。質問や相談がすぐにでき、応答も迅速です。
面接や履歴書のサポートも手厚く、転職活動が初めての方や不安を感じる方にも強くおすすめできます。
日本最大級の12万件以上の求人数を誇る転職サイト!友達に勧めたいサービスランキング第1位

- 「友達に勧めたいサービス」で堂々の1位
- 日本最大級の12万件以上の求人を提供
- 忙しい日でも、LINEで気軽に相談可能
レバウェル看護師(旧:看護のお仕事)は、転職を考える看護師さんに手厚いサービスを提供する業界トップクラスの転職サイトです。その信頼性から「友達に勧めたいサービスランキング」で1位に輝いています。
求人数は驚異の12万件以上あり、その数は日本最大級。加えて、病院のリアルな口コミやスタッフの声も確認できます。
そして何より、忙しい看護師さんでもLINEで気軽に相談ができますし、キャリアアドバイザーからも丁寧な情報提供が受けられます。
顧客満足度NO1!累計100万人以上の看護師が利用する人気の転職サイト

- 累計100万人以上の看護師が利用
- 地域専任の看護師専門キャリアパートナーが担当
- 介護施設など病院以外の求人が豊富
ナース専科 転職(旧ナース人材バンク)は、2023年のオリコン顧客満足度調査で看護師転職部門で総合第1位を獲得。累計100万人以上の看護師が利用しており、看護師転職界の信頼性を証明しています。
地域専任の看護師専門キャリアパートナーが個々のニーズに合わせて最適なアドバイスを提供します。また、病院だけでなく、介護施設など多種多様な求人があり、全国どこでも活躍の場が見つかります。
転職を検討する看護師さんにとって、確かなサポートと多様な選択肢を提供するこのサイトは、一考の価値があります。
9. まとめ
今回の記事では、看護師の退職手続きについて説明しました。
「看護師を辞めるときの手続きがよくわからない」「退職時に返却するものと受け取るものは何があるの?」といった悩みを抱える方は、本記事で紹介した下記の重要なポイントをおさえることで、転職活動をスムーズに進めることができます。
- 退職時に返却するもの(健康保険証、通勤定期券、職場支給の備品)と受け取るもの(雇用保険被保険者証、源泉徴収票、年金手帳、離職票)を把握しておく
- 離職期間の有無と雇用保険加入期間によって、年金・健康保険・失業手当の手続き方法が異なることを理解する
- 退職後の住民税や所得税の支払い方法を確認し、必要な手続きを行う
- 円満退職とスムーズな転職のために、看護師転職サイトを活用する
円満に退職するためには適切な退職手続きが不可欠ですが、慣れない手続きに戸惑う看護師も少なくありません。そのため、看護師転職サイトを活用してキャリアアドバイザーに悩みを相談したり、条件に合った職場を効率良く探すことをおすすめします。
JOBANUSがおすすめする看護師転職サイト3社は以下のとおりです。迷ったらこの3社を併用することをおすすめします。
ぜひこの記事の転職を成功させるためのポイントを参考に、職探しにチャレンジしてください。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。